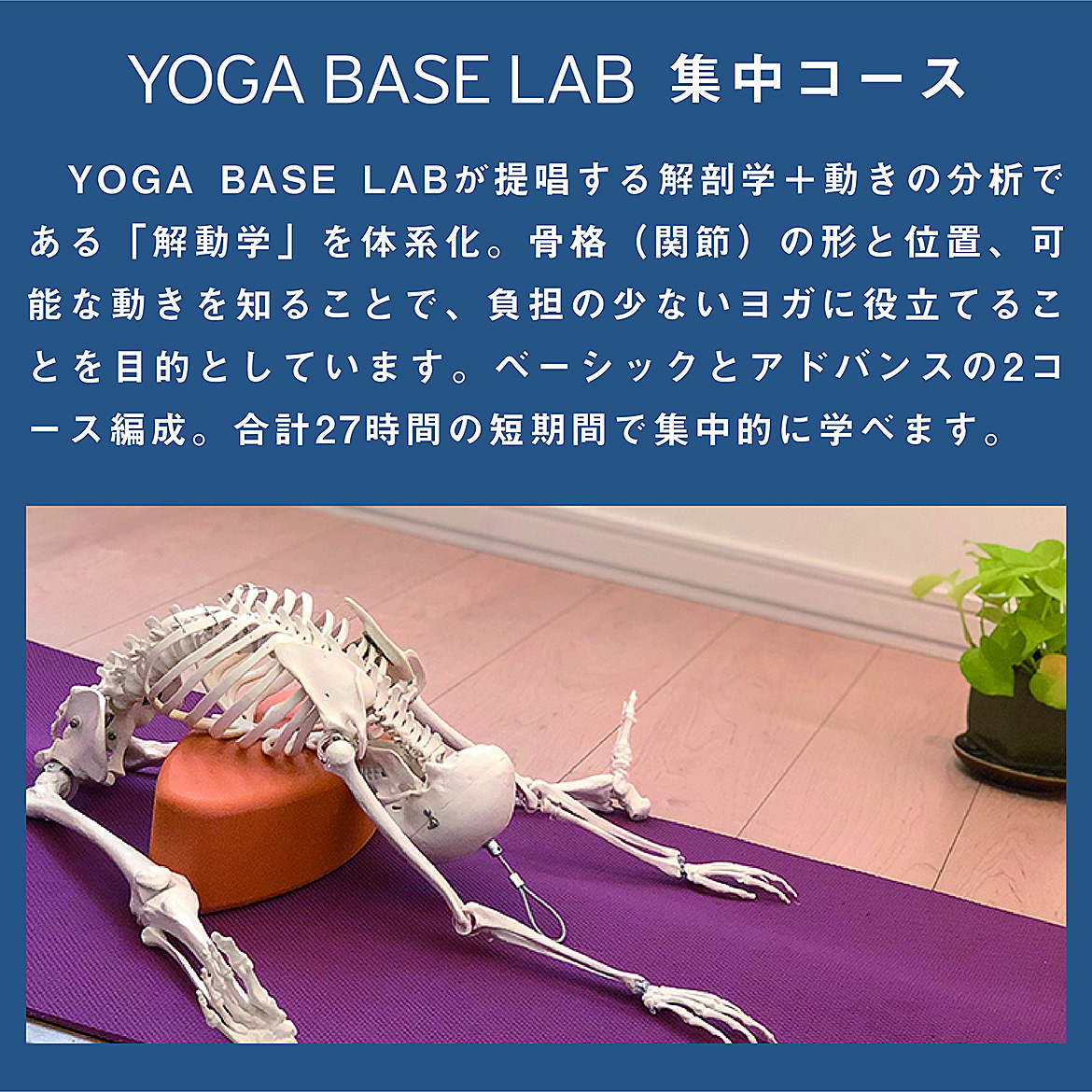ハスヨガマガジンの「ヨガの練習で耳にする「自分と向き合う」方法は?具体策3つ」では、目を閉じることによって、身体の部分にフォーカスして緊張させてしまうことがあるとお伝えしました。 そこでこの記事では、自分と向き合うときに目を閉じることにどのような意味があるのか、それがどう影響するのかについて考えてみます。

自分と向き合うのに必要なこと
そもそも「自分と向き合う」「自分を内観する」「自分を感じる」といった行為は、具体的には何をすればいいのでしょうか?
パソコンに向かって文章を書いている今の筆者であれば、「目の前にモニターがあるな」「キーボードを打っていたらだんだん肩が凝ってきたな」「腰も痛くなってきたな」「集中力が続かなくて他のことに目がいくな」といったことがそれに当たるのでしょう。
あるいは「今やっていることは自分がやりたいか否か」というような、大意で向き合うとすることもあるでしょう。
いずれにしろ、自分と向き合うためにやるのは、感じていることや身に起こっていることを情報として受け取るに終始するといえます。
私たちは常時情報を収集をしている
さて、この情報を受け取るということがシンプルにして厄介です。私たちは感覚器官でもって多種多様な情報を常に受け取り続けています。
視覚、嗅覚、聴覚、味覚、触覚、その他の全身の筋感覚などで感じたこと全てが情報であり、私たちの中にその情報が入ってくることは起きている限り途切れません。
あまりにも膨大なので皆さんのほとんどが、現在進行形で情報を受け取り続けているという自覚がないでしょう。
自分と向き合うというのは、常に行っている情報収集を意識的にやるということでもあります。
目を閉じれば視覚情報をシャットアウトできる
自分と向き合うときによく目を閉じてと言われるのは、この膨大な情報の一つである視覚から流れてくるものをシャットアウトするため。
視覚は全情報の中でもかなりの幅を占めていて、私たちは多くの行動の判断を視覚に頼って行っています。
そのため目を閉じれば、情報量を減らして他の感覚器官からの情報に集中できるようになります。
また、情報が厳選されて選択しやすくなるので、次の行動に繋がるというメリットもあります。
見えないことで情報を取りにいこうとしてしまう
一方で視覚がなくなることによって、集中しすぎるというデメリットも生じます。
目を閉じた暗い中で集中しようとすると、「他の感覚はどうだろう」「今感じているのはこれでいいのだろうか」などと気を回すようになることがあります。
これは情報を受け取るのではなく、存在するかどうかもわからない情報を探して、自分から取りにいこうとしているようなもの。
情報を受け取るとは別物です。
だからこそ、視覚があると気が紛れて、集中しすぎずにすむというメリットがあるのです。
おわりに
「自分と向き合う→自分に起こっていること、感じていることを情報として受け取る→あるがままを受け入れる」とするなら、情報を自分から取りにいくのをやめて、ただ受け取るだけを甘受できる環境を作れるのが理想的です。
とはいっても、実践するのは難しいもの。
なので、「落ち着くためにまずは目を閉じる」「情報を自分から探しにいっていると気付いたら目を開ける」など、臨機応変に使い分けてみるのもいいでしょう。
↓合わせて読みたい↓
↓元ネタのハスヨガマガジンの記事↓
↓身体の機能性を重視した陰ヨガを体験するなら↓
↓解動学(解剖学+動作の分析)を学ぶなら↓